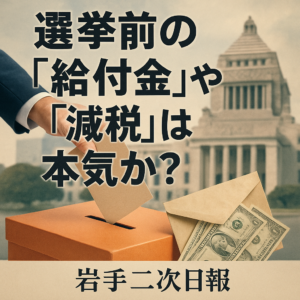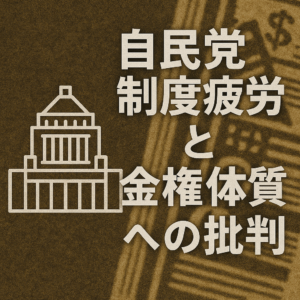「省庁訪問で叫んだ“常識”」という名の非常識※岩手二次日報
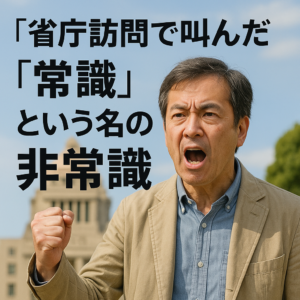 最近、日本改革党のくつざわ氏が行った省庁訪問の報告が話題になっています。
最近、日本改革党のくつざわ氏が行った省庁訪問の報告が話題になっています。
財務省や外務省をはじめ、農水省、厚労省、法務省と、まさに「全方位」で直談判をして回るという行動力。
国民の声がどれほど政治に反映されているのかという点で、大きな疑問符がついています。
減税と手取りの話、これは“生活の話”です
財務省への訴えは、「減税をしてくれ」「国民の手取りを減らすな」という極めてシンプルかつ現実的な要求。
確かに、庶民の感覚としては“政府の財布が膨れる一方で、自分たちの財布は薄くなる”ことへの不満は増加の一途をたどっています。
問題なのは、その政策決定の「根拠」や「透明性」があまりにも見えないこと。
最近捲れた事実としてただ一人の財務省出身の国会議員が全て決めていたという事実。
減税を避ける理由、財政健全化の裏付け──そのあたりをきちんと説明してほしい、というあたりまえの声が代弁された形です。
海外支援に「ちょっと待った」の声
外務省に対しては、日本が行っている約2.5兆円にも及ぶ海外支援について、「なんで他国の橋を日本人が建てるのか」という問いかけ。
これは、子供でもわかる常識論であり、わざわざ超えに出して言わなければならないほど日本の外務省は腐敗しています。
もちろん外交的意義や国益もあるでしょう。
しかし、特に説明もなく勝手に突っ走る外務省の憲法無視の暴挙には我慢がならないというのが国民の声です。
「国内がここまで疲弊しているのに、優先順位が違うんじゃないか?」という声を無視し続けることが、政府と国民との溝を深くしていることは間違いありません。
外務省は30年前から売国の象徴と言われています。
もちろん、数名まともな役人もいましたが組織の前には無力です。
であれば、やはり解体すべきだという声で国内はあふれかえっています。
レジ袋・備蓄米・難民問題──あらゆる政策に「生活者目線」を
農水省には、備蓄米の売却手法に対しての疑問。
厚労省には、レジ袋有料化や外国人への生活保護のあり方について。
法務省には、難民審査の迅速化と透明性の向上を求める声。
いずれも「政治が生活を知らなすぎる」と感じている層にとって、ストレートに刺さる内容です。
一つひとつの要求が「正しいかどうか」というより、「どうしてこういう不満が出てきてしまうのか」をしっかりと読み取る必要があると思います。
これは単なるデモ活動ではなく、“生活者の常識”から見た政治の非常識に対する警告です。
いま必要なのは「法令」より「民意」
最後に触れておきたいのは、今回の活動に込められた根本的な問い。
「法律ではなく省令や通達で、実質的に立法権を行使している官僚組織は、このままで良いのか?」というもの。
行政が立法を事実上握っているこの構造こそが、“国民不在”の象徴。
だからこそ、「人事権を国民に取り戻す」「第三者機関でのチェックを」などの意見が出てくるのです。
パフォーマンスに見えるかもしれない行動の中にも、「もう騙されない」という強い決意がどんどんと上がってきています。
官僚支配の現状を「泥縄」と皮肉る声もありますが、国民が声をあげ、関心を持ち、直接訴える動きが広がること──それこそが、制度の根幹を揺さぶる本当の「第一歩」です。