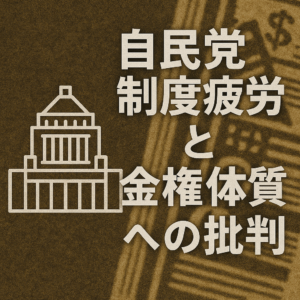もう通用しない「国民の借金」論※岩手二次日報
 政府の債務が1323兆円に達し、「過去最大」と報じられました。
政府の債務が1323兆円に達し、「過去最大」と報じられました。
しかし、最近のニュースでは、以前よく使われていた「国民一人あたり○○万円の借金」という表現が、ほとんど見られなくなっています。
理由は明白です。国民が、そこそこ賢くなってきたからです。
SNSや動画プラットフォームを通じて、以前は専門家しか触れなかったような「財政のカラクリ」について、多くの人が理解し始めています。
例えば、「政府の借金=国民の借金」という言い回しは、明らかに誤解を誘うものでした。
実際には、政府の借金は、主に日本銀行や国内の金融機関、そして国民自身が保有する国債によるものです。
つまり、債務であると同時に、それは国民の資産でもあるというのが実態です。
昔なら「借金が膨らんでるぞー!破綻するぞー!」と騒げば、国民は素直に財政緊縮を受け入れたかもしれません。
でも今は、「それ誰に借りてるの?」とツッコミが入ります。財務省としても、もう無理筋のプロパガンダは打てなくなってきたのでしょう。
こうした報道のトーンの変化は歓迎すべきですが、逆に言えば、これまで国民が長年にわたり、都合よくミスリードされてきたということでもあります。
そしてそれを主導してきたのが、財務省をはじめとした中央官僚たちでした。
国民に嘘をつき続けてきた報いは、そろそろ受けてもらうべき時期です。
特定の省庁に限らず、すべての中央官庁は一度リセットすべき段階にきています。
選挙で政治家を選ぶように、官僚の要職も公開選抜制にして、国民が選べるようにするべきではないでしょうか。
知識を持った国民が増えれば、情報操作は効かなくなります。
そして、行政のあり方そのものも、もっと根本から見直される必要がある。
今回の報道スタイルの変化は、その大きな転換点を示しているのかもしれません。