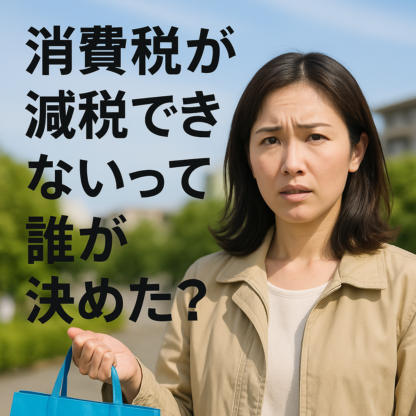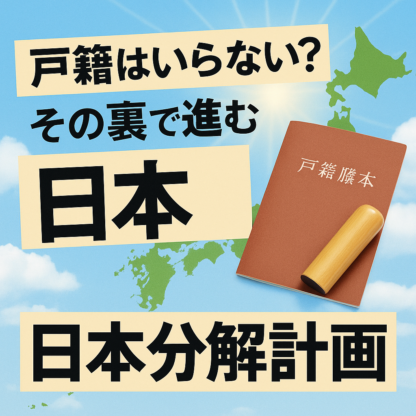大船渡の山火事、誰のせいで焦げたのか?※岩手二次日報
 岩手県大船渡市で起きた大規模林野火災。延焼面積は3,370ヘクタールと、平成以降で最大規模。だが、報道の論調は「制度の期間が短い」「支援が足りない」で終わっていて、肝心の“なぜ燃えたか”に目を向けていない。
岩手県大船渡市で起きた大規模林野火災。延焼面積は3,370ヘクタールと、平成以降で最大規模。だが、報道の論調は「制度の期間が短い」「支援が足りない」で終わっていて、肝心の“なぜ燃えたか”に目を向けていない。
いやいや、焼け跡の復旧スケジュールを語る前に、「なんでこんなに燃え広がったのか」を調べるのが筋ってもんじゃないの?どうもその「核心」に国もメディアも触れたがらない。それが妙に鼻につく。
■ 復旧期間の短さより「原因究明」の方が急務
今回の復旧事業は、人工林を対象にした「森林災害復旧事業」。期間は伐採と搬出が4年、造林が5年――って、数字の上ではそれなりに長く見える。ところが始点が「災害が起きた年度」からカウントされるため、実質的に作業期間がカットされてしまう。これに市が懸念を示している。
確かに制度の仕組みとしては不親切。作業人員の確保だって一苦労だろうし、所有者との調整も簡単ではない。が、それより先に手をつけるべきは“火災の原因”だ。
ネット上には「放火では?」という声が山ほどある。しかも単なる火遊びどころではなく、「レーザーを使った放火の証拠写真」まで飛び交っている。もちろんフェイクも混じってるだろうが、どれひとつとして真面目に検証された形跡がない。
■ 大船渡だけじゃない「不自然な火災」が全国で頻発中
大船渡に限った話じゃない。北海道、九州、四国、関西でも林野火災のニュースが相次いでいる。火の回り方、風の強さ、火点の多さ――どれをとっても、単なる自然発火では説明がつかない事例が続出している。
そして、なぜか「火災の原因」はサラッと流され、復旧費用や制度の不備ばかりが語られる。放火や、それに類する人為的な仕掛けを真剣に疑ってもいい頃だ。
「都市伝説」と切って捨てられていたことが、今ではニュースとして報じられていることも少なくない。つまり“陰謀論”のフリをした“先出しリーク”の可能性すらあるってこと。
■ 国政、ここまで無関心でいいのか
国がやる気ゼロなのは、もう確定だろう。大船渡市が「柔軟な支援を」と国に要請しているが、そもそも国の反応は毎度「事務的」「マニュアル通り」「担当レベルで検討します」の三拍子。
火災後すぐに外国企業による土地取得やら開発の話が出てきているというウワサもあるが、そういう話こそ即時調査すべきだ。だって、燃えた山が再開発で“美味しく”使われるなら、これはもう偶然じゃ済まない。
国がその気なら、証拠隠滅も“制度の範囲内”でやり放題だ。焼け野原の裏で何が進んでいるのか、我々市民が監視の目を緩めたら終わりである。
■ 「地方の火災」ではない。日本全体の問題
大船渡市の問題は、たまたま今回は「岩手」だっただけ。明日はあなたの町が燃えるかもしれない。そういう想定で考えるべき。
そして、芸能ネタや政界の茶番劇に目を奪われてる間に、大事な土地や水源が“焼かれて”奪われていく。この手の火災は、もう“気候変動”とか“乾燥による自然発火”とかいうテンプレでは片付かない段階に入ってる。
■ まとめ:復旧よりも、「監視」と「告発」が先だ
市が「復旧計画に柔軟性を」とか「作業人員が足りない」と言っているのは分かる。だが、その前に火災原因の徹底究明を国に求めなければ、次もまた同じことが起きる。
いや、むしろ次はもっと手際よく、もっと広く、燃やされるかもしれない。だからこそ、今動くべき。
復旧計画に気を取られている暇なんて、実は一秒もないのである。