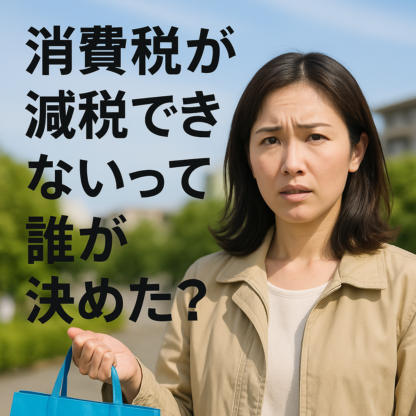盛岡文士劇、変えるべきは「形」より「中身」※岩手二次日報
盛岡の冬の風物詩、盛岡文士劇。その運営サイドが「見直し検討会」なるものを立ち上げたそうです。目的は、出演者やスタッフの負担軽減、公演内容の再構築……とまぁ、聞こえは良いですが、実態はどうやら問題の本質を見失ってるご様子。
盛岡の舞台芸術、どこに向かってるの?
盛岡市松尾町の盛岡劇場で行われるこの文士劇、衣装や小道具の費用がかさんできた、人件費も高い、チケットが夜に売れない…と、泣き言が並びます。でも、それって今に始まったことじゃない。物価高騰は全国的な問題。むしろ、その環境下でどう魅せるか、どう客を呼び込むかが問われるべきです。
検討会とやらが「新たな公演の形を模索する」と言っていますが、正直それではピントがずれてます。問題は形じゃない、「中身」でしょう。演目、時間、訴求力、そして何より宣伝。お客さんの目線を完全に置き去りにしてる演出、誰が観に来るの?って話です。
若年層が来ない? そりゃそうだ
「若い客層を取り込めていない」という自覚があるのに、3時間の長尺時代劇を延々と続けるとか、もはや反省してないのと同じです。TikTokが主戦場の若者が3時間耐えると思ってるのかい? せめてハーフタイムショーでも挟んだらどうかと皮肉の一つも言いたくなります。
イノベーションってのは、「新しいことをやる」ことじゃない。「今のやり方じゃダメだ」とちゃんと自覚して「必要な変化を起こす」こと。見た目だけの刷新ではなく、客の心をどうつかむかを徹底的に考えることが求められています。
盛岡市政や国の文化政策にも一言
地方文化の現場がこうして疲弊していく背景には、自治体の支援不足も見逃せません。チケットが売れないから夜公演が厳しい? 公共交通が減便されてる? 地域振興を語るなら、まずそこ支えようよ、国政。文化を守るって言葉がポスターの中だけなら、それはもはや嘘と同じです。
結局のところ「お客様目線」が抜けてる
論点は明快。「新たな形」ではない、「新たな視点」なんです。宣伝方法ひとつ取っても、もっとSNSや動画、ストリート施策と絡めてやれば反応は変わる。インスタライブでも、YouTubeの裏話でも、「見たい!」と思わせる動線を組まなきゃ。
伝統に甘えて、古いやり方を「文化」って言い換えてごまかしてちゃ、次の100年は来ません。盛岡文士劇が続いていくためには、「面白い」「行ってみたい」と思わせる仕掛けを作ること。観客は待ってくれませんよ。